9月~10月に異動や再任用の調査があるが、同時にこのころ産育休で休んでいる人への来年度育休の意向調査も行われる。ここで、来年度も育休を取ると決定した人がいた場合、管理職は早めのこの時期から臨任確保に動くことになる。安心して担任や教科を任せることができる臨任を早めに押さえておくということだ。もちろん継続勤務ができれば、臨任本人にも学校としても良いのだろうが、様々な事情で継続できないことになった場合、管理職間での情報交換が行われて、現職の臨任に打診がある。早い人はこの段階で来年度の勤務校も内定してしまう。
この秋の時期を過ぎると、教育委員会から正規教員の異動内示が出る冬(1~2月)まで臨任確保の動きは水面下になってしまう。
そして、3月になると育休代替臨任の決まっていないところは、欠員が出ないように臨任を探さなければならない。教育委員会の担当者が大忙しの時期だ。多くの自治体が3月中旬までに正規教員の最終内示を終えるが、同時に臨任も決定していなければ、来年度の校内人事を確定するのが難しくなってしまう。
3月下旬になると、さすがに臨任募集は減る。この時期まで欠員が生じている学校は、標準配当ではない「加配」と呼ばれる習熟度・日本語・特別支援・専科などの担任ではないポジションを欠員にして、臨任を待つしかない状況になっている。始業式・授業開始までにどうしても臨任が見つからない場合は非常勤であてがうこともある。
4月からは、新たに産育休の申請をした人がいると、その休業期間の代替臨任が募集されることになる。また、少数ではあるが初任者で6ヶ月を待たずに辞めてしまうこともあるようだ。この場合、学校側は欠員臨任の補充を待ち望むことになる。
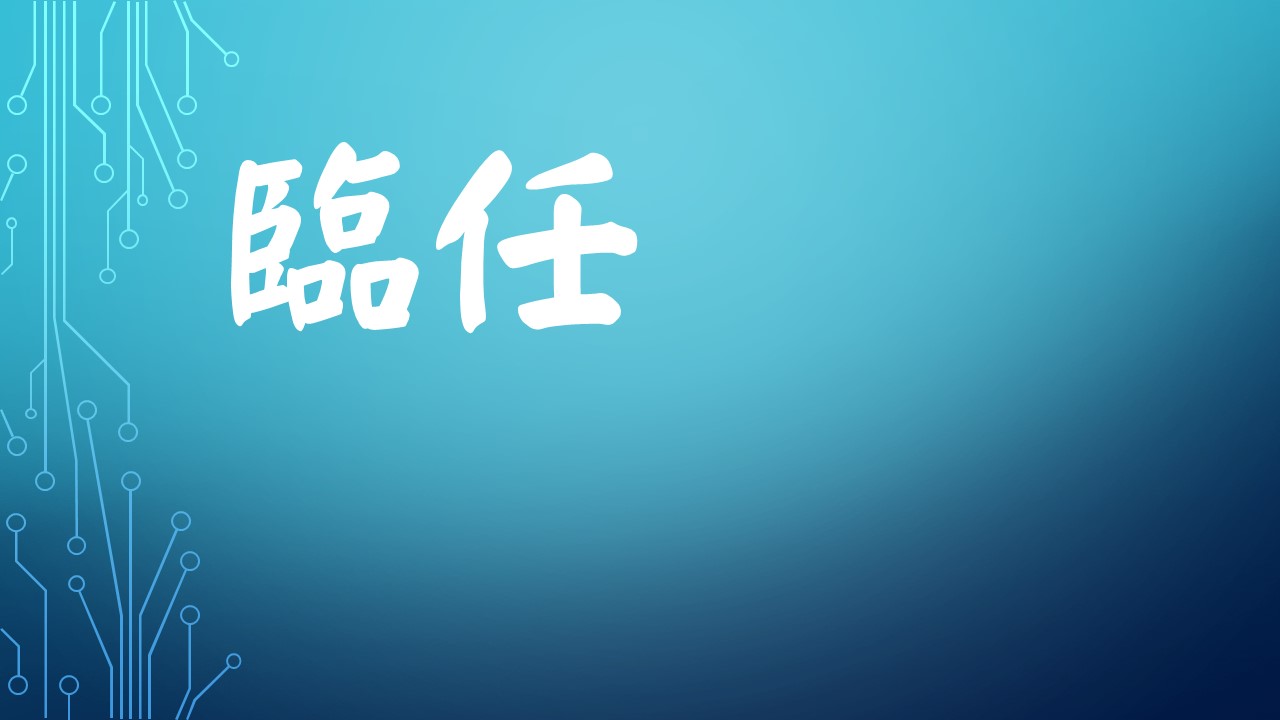
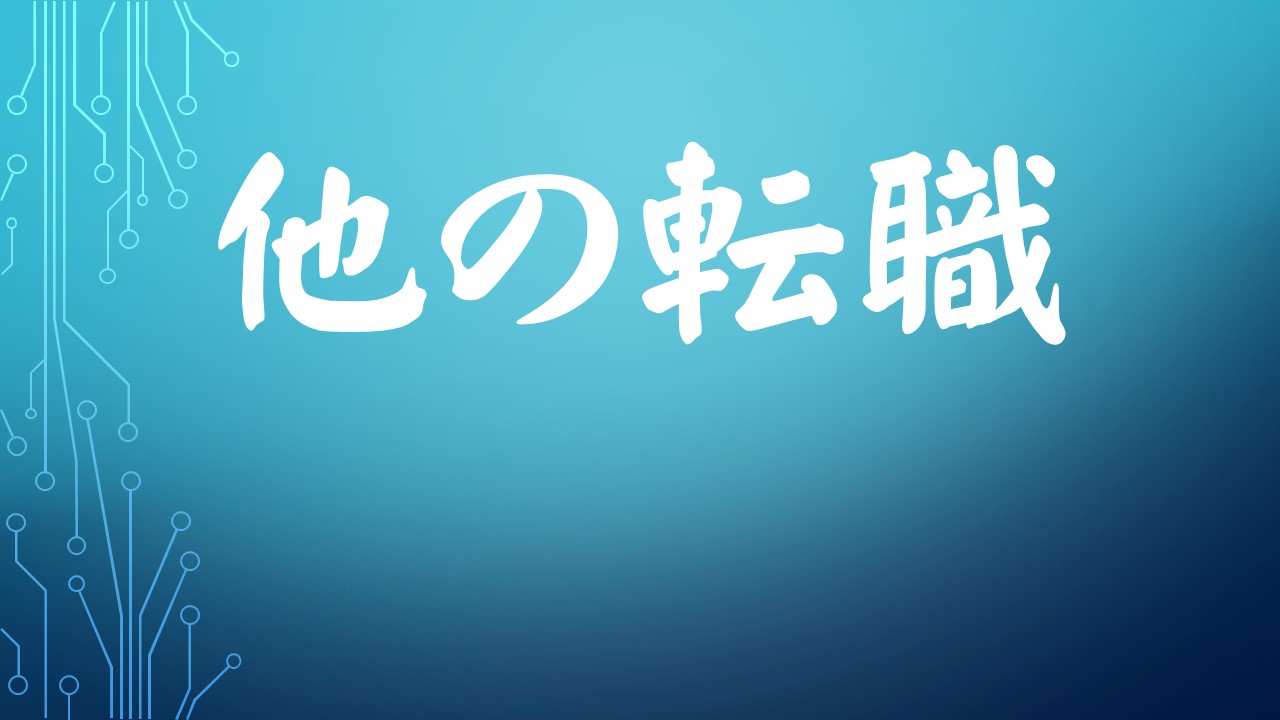
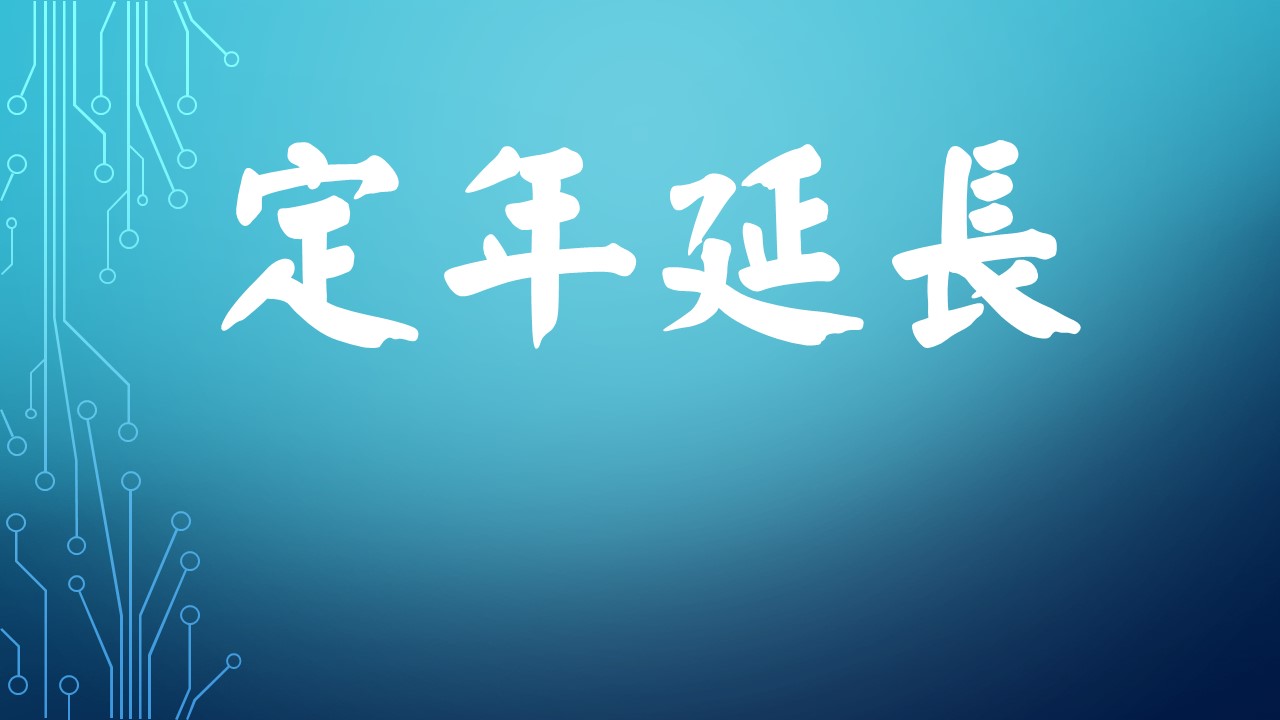
コメント